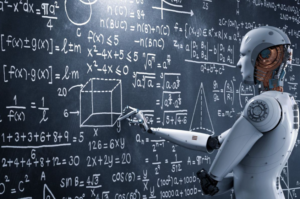皆さんこんにちは!
古河市にある塾、学習塾Luce(ルーチェ)です☆
古河市で学習塾を営む私のもとに、近年、お子さんの不登校や学校での悩みを相談に来られる保護者の方が増えています。その中で、多くの保護者の方が関心を寄せるのが、フリースクールという選択肢です。しかし、「フリースクールってどんなところ?」「普通の学校とどう違うの?」「通わせることで、子どもにどんなメリットがあるの?」といった疑問を持つ方がほとんどです。
今回のブログでは、古河市の学習塾塾長という立場から、学習指導や受験対策だけではなく、多くの子どもたちと保護者の方々の悩みに寄り添ってきた経験をもとに、フリースクールとは何か、その役割、そしてお子さんと保護者の方にとってのフリースクールとの関わり方について、お話ししたいと思います。この記事が、フリースクールという選択肢を考えている保護者の皆さまの一助となれば幸いです。
◆フリースクールとは何か?

まず、フリースクールの基本的な定義から始めましょう。フリースクールとは、何らかの理由で学校に通うことが難しい、あるいは学校の枠組みに合わない子どもたちのための、学校以外の教育・居場所の選択肢です。公的な教育機関ではないため、その運営形態や活動内容は様々です。
学校に馴染めない、いじめにあった、病気や心身の不調、発達の凸凹、あるいは学校のカリキュラムやルールに窮屈さを感じるなど、子どもたちが学校に行けなくなる理由は多岐にわたります。フリースクールは、そうした子どもたち一人ひとりの個性や状況に寄り添い、それぞれのペースで学んだり、他者と関わったりできる場所を提供しています。
公立学校では、どうしても画一的な指導や集団での行動が中心になりがちです。しかし、フリースクールでは、小規模な集団で個々のペースを尊重した学習が行われたり、遊びや体験学習、地域との交流など、教科の枠を超えた様々な活動が行われたりします。この**「個」を尊重する姿勢**こそが、フリースクールの最大の特徴であり、公立学校との決定的な違いと言えるでしょう。
◆なぜ今、フリースクールの必要性が高まっているのか?
文部科学省の調査によると、不登校の子どもの数は年々増加の一途をたどっています。これは決して特別なことではなく、現代社会が抱える様々な要因が複合的に絡み合った結果だと私は考えています。
社会の変化と子どもたちの多様性
現代社会は、情報過多で変化のスピードが速く、子どもたちを取り巻く環境も複雑化しています。SNSの普及による人間関係のトラブル、受験競争の激化、そして何より、一人ひとりの個性や価値観が多様化しているにもかかわらず、学校という集団生活の場では、まだまだ画一的な価値観が求められがちです。
例えば、発達障害の傾向がある子どもの中には、集団行動や長時間座学が苦手な子もいます。そうした子どもたちにとって、既存の学校の枠組みは窮屈に感じられ、ストレスの原因となることがあります。また、HSC(Highly Sensitive Child)と呼ばれる、非常に敏感で感受性が豊かな子どもたちもいます。彼らは、些細な人間関係の摩擦や音、光にも過敏に反応し、学校という環境で心身のバランスを崩してしまうことがあります。
このような多様な子どもたちのニーズに、公立学校がすべて応えることは難しいのが現実です。そこで、子どもたち一人ひとりの特性やペースに合わせた学びの場として、フリースクールの役割が重要性を増しているのです。
◆フリースクールが果たす3つの役割

私が考えるフリースクールの役割は、大きく分けて以下の3つです。
1. お子さんにとっての「安心できる居場所」
学校に行けなくなった子どもたちが最も必要としているのは、「自分を肯定できる場所」です。学校を休むという選択をした後、子どもたちは「自分はダメな子だ」「もう学校には戻れない」といった自己否定的な感情に陥りがちです。
フリースクールは、そうした子どもたちに「休んでいいんだよ」「ここにいてもいいんだよ」というメッセージを伝えてくれる場所です。学習の遅れを気にすることなく、誰かに無理に合わせる必要もなく、ただそこにいるだけで許される場所。これが、お子さんにとってのフリースクールの第一の役割です。この安心感の中で、子どもたちは徐々に自己肯定感を取り戻し、次のステップへと進むエネルギーを蓄えることができます。
2. 「学び」の再構築
フリースクールの活動は、教科の学習だけではありません。多くの場合、子どもたちの興味や関心に合わせて、様々な活動が取り入れられています。例えば、料理、工作、プログラミング、地域のボランティア活動、そして何より「遊び」も大切な学びの時間です。
学校の授業でつまづいてしまったお子さんでも、少人数制の指導で、わからないところを丁寧に教えてもらえることで、再び学習意欲が湧いてくることがあります。また、座学だけでなく、体験を通して学ぶことで、知識がより深く定着することもあります。
大切なのは、「学び」は学校の教室の中だけで行われるものではない、ということをお子さん自身が実感することです。この気づきが、将来にわたって自ら学ぶ力を育む土台となります。
3. 将来への「社会性」を育む
「フリースクールに通うと、社会性が身につかないのでは?」と心配される保護者の方もいらっしゃいます。しかし、それは大きな誤解です。
フリースクールも、様々な年齢や背景を持つ子どもたちが集まる小さな社会です。学校のように大人数が集まるわけではありませんが、少人数のグループの中で、他者と関わり、意見を交換し、時にはぶつかり合う経験は、お子さんの社会性を育む上で非常に重要です。
フリースクールでは、子どもたちが自ら活動内容を企画したり、ルールを決めたりすることも珍しくありません。こうした主体的な経験は、コミュニケーション能力や問題解決能力を高め、将来、社会に出るための大切なスキルとなります。
また、フリースクールのスタッフは、単なる教師ではなく、お子さん一人ひとりの個性を受け止め、そのありのままの姿を承認してくれます。この経験は、お子さんが将来、どのような環境に身を置いても、自分らしく生きるための自信につながるはずです。
親御さんへのメッセージ:フリースクールを「卒業」した先にある未来

フリースクールは、お子さんが一生通い続ける場所ではありません。あくまでも、次のステップへ進むための通過点、あるいは充電期間だと私は考えています。
フリースクールに通う中で、お子さんが再び学校へ通いたいという気持ちになるかもしれません。あるいは、高校進学や就職という次の目標を見つけるかもしれません。
私が経営する学習塾にも、フリースクールに通いながら、週に数回、学習指導を受けに来るお子さんがいます。彼らは、フリースクールで自己肯定感を取り戻し、落ち着いた環境で学習に集中できるようになった結果、学力も大きく伸びています。
保護者の方へお願いしたいこと
お子さんがフリースクールを検討する際、または通い始めた後、保護者の皆さまには以下のことを心に留めておいていただきたいです。
- お子さんの気持ちを最優先に: フリースクールに通うかどうかの決定は、お子さんの意思を尊重してください。まずは一緒に見学に行き、お子さんが「ここなら行ってもいいかな」と思える場所を見つけることが大切です。
- 完璧を求めない: フリースクールは、お子さんのすべてを解決してくれる魔法の場所ではありません。お子さんの心身の状態は日々変化します。焦らず、ゆっくりと、お子さんのペースを見守ってあげてください。
- 社会との繋がりを意識する: フリースクールに通うお子さんには、社会との接点が少なくなりがちです。地域のお祭りやボランティア活動など、様々な体験を通して、社会との繋がりを意識的に持たせてあげてください。
- 保護者自身も休息を: お子さんが不登校になると、保護者の方も精神的に追い詰められがちです。一人で抱え込まず、支援機関や信頼できる人に相談してください。保護者の方が心身ともに健康であることが、お子さんを支える上で最も重要です。
お子さんへのメッセージ:君の「好き」を見つける旅に出よう
もし、今、学校に行きづらさを感じているなら、それは決して君が悪いわけではありません。学校という場所が、今の君には合わなかっただけのことです。
フリースクールは、君が本当に好きなこと、興味のあることを見つけるための場所です。
- もし、ゲームが好きなら、ゲームをプログラミングで作ってみる。
- もし、絵を描くのが好きなら、大きなキャンバスに思う存分描いてみる。
- もし、体を動かすのが好きなら、近くの公園で思う存分サッカーをする。
フリースクールでは、そんな君の「好き」を、全力で応援してくれる大人がいます。
学校で学ぶ教科の勉強も大切だけど、君自身の心を大切にすることが、もっともっと大切です。
「学校に行かなきゃ」という気持ちに縛られなくていい。
まずは、君の心が「行きたい」と思える場所を、一緒に探してみよう。
古河市とフリースクールの未来
古河市でも、フリースクールやオルタナティブな学びの場への関心は高まっています。しかし、まだまだその数は少なく、情報も十分ではありません。私は、学習塾を運営する傍ら、古河市の子どもたちが多様な学びの選択肢を持てるよう、フリースクール関係者や地域社会と連携し、より良い教育環境を築いていくことが重要だと考えています。
古河市の子どもたちが、画一的な価値観に縛られることなく、それぞれの個性や才能を伸ばし、将来にわたって幸せに生きるための力を育むこと。そのために、フリースクールは欠かせない存在となりつつあります。
最後に、もしお子さんのことでお悩みがあれば、一人で抱え込まず、まずは私のような地域の専門家、または地域の教育相談窓口に相談してみてください。
■フリースクールLuce
https://luce-dream.com/freeschool/
このブログが、お子さんと保護者の皆さまの未来を拓く一助となれば幸いです。
————————————————————————————————————–
学習塾Luce(ルーチェ)
〒306-0225 茨城県古河市磯部1615−1
電話番号: 050-1402-3694
https://luce-dream.com/
古河、結城、八千代町から近くの塾をお探しなら、 学習塾Luce(ルーチェ)がおすすめ!
————————————————————————————————————–