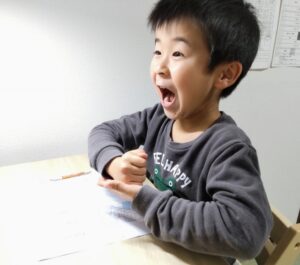皆さんこんにちは!
古河市にある塾、学習塾Luce(ルーチェ)です☆
お子さんが算数でつまずいていませんか?「うちの子、計算はできるけど文章題になるとさっぱりで…」「新しい単元に入ると、前の内容を忘れてしまうみたい」といったお悩みを持つ親御さんは少なくありません。算数は、積み重ねが大切な科目です。どこかでつまづいてしまうと、その後の学習にも大きな影響を与えてしまいます。
この記事では、算数が苦手な小学生のお子さんを持つ親御さん向けに、ご家庭での効果的な学習方法と、学習塾を上手に活用するヒントをお届けします。お子さんが算数を楽しめるようになるための具体的なアプローチを、ぜひご一緒に考えていきましょう。
≪目次≫
●算数が苦手になる原因を理解しよう
●自宅学習で算数を得意にするためのアプローチ
●学習塾を上手に活用する方法
●算数嫌いを克服するための親御さんの心構え
●おわりに
算数が苦手になる原因を理解しよう
まず、お子さんがなぜ算数が苦手になってしまうのか、その原因を考えてみましょう。原因を特定することで、適切な対策を立てることができます。
1. 基礎概念の理解不足
算数では、数や図形、量といった基本的な概念を正確に理解していることが大前提となります。例えば、「10進法」の意味や「位取り」のルール、分数の「分母」と「分子」がそれぞれ何を表すのかといった基礎が曖昧なまま進んでしまうと、その後の複雑な計算や問題理解でつまずいてしまいます。
- 具体例:
- 繰り上がりの足し算や繰り下がりの引き算で指を使って数えている。
- 九九を丸暗記しているだけで、その意味(例えば が を 回足すことと同じ)を理解していない。
- 面積の公式は覚えているが、なぜその公式で面積が求められるのかを説明できない。
2. 具体的なイメージが掴めない
算数の概念は抽象的になりがちです。特に低学年のうちは、具体物を使って体験的に学ぶことが非常に重要です。例えば、「足し算」は「合わせる」こと、「引き算」は「減らす」ことや「違いを求める」こと、「掛け算」は「同じものをいくつ分」と考えることができれば、問題文を読んだ時に具体的なイメージが浮かびやすくなります。
- 具体例:
- 文章題を読んでも、それが足し算なのか引き算なのか、どのような計算をすれば良いのかが分からない。
- 時計の読み方や時間の計算が苦手。
- 立体図形の問題で、どの面がどこに当たるのか想像できない。
3. 暗記学習になっている
算数は「考える力」を養う科目です。公式や計算方法をただ丸暗記するだけでは、少し応用問題が出ただけで手が止まってしまいます。なぜその公式を使うのか、なぜその計算方法で解けるのか、といった「理由」を理解することが大切です。
- 具体例:
- 計算問題は解けるが、同じ計算を使う文章題になると間違える。
- 教科書の例題は真似して解けるが、少し数字が変わったり、問い方が変わったりすると分からなくなる。
4. 集中力の欠如や飽きやすさ
小学生は集中力が続く時間が限られています。また、苦手なことに対しては特にモチベーションが維持しにくいものです。学習中に気が散ってしまったり、すぐに飽きてしまったりすることも、算数嫌いにつながることがあります。
- 具体例:
- 宿題を始めるまでに時間がかかる。
- 途中で席を立ったり、他のことを始めてしまったりする。
- 簡単な計算ミスが多い。
5. 苦手意識によるモチベーションの低下
一度「苦手だ」「できない」と感じてしまうと、算数に対するモチベーションが大きく低下してしまいます。そうなると、新しいことを学ぼうとする意欲が薄れ、さらに苦手意識を強めるという悪循環に陥りやすくなります。
- 具体例:
- 算数の時間になると、お腹が痛くなったり頭が痛くなったりする。
- 「どうせできないから」と最初から諦めてしまう。
- 「算数なんて嫌い」と口に出すようになる。
自宅学習で算数を得意にするためのアプローチ

お子さんが算数を好きになり、得意になるためには、ご家庭でのサポートが非常に重要です。ここでは、具体的な自宅学習のアプローチをいくつかご紹介します。
1. 「なぜ?」を大切にする学習
概念理解を深める質問の投げかけ
お子さんが問題に取り組む際、答えだけでなく、**「なぜその答えになるのか」「どうやって考えたのか」**を尋ねてみましょう。例えば、 という計算に対して、「どうして になるの?」「何か他に になる組み合わせはあるかな?」と問いかけることで、単なる計算練習に終わらせず、数の構成について深く考えさせるきっかけを与えます。文章題では、「この問題は何を求めたいの?」「何と何が分かっているの?」といった質問で、問題文から情報を読み取る練習をさせます。
具体物を活用したイメージ作り
算数の概念は、目に見えない抽象的なものが多いです。これらを具体的にイメージできるよう、身近なものを活用しましょう。
- 数と計算:
- おはじきやブロック: 足し算、引き算、掛け算、割り算の導入に最適です。実際に数を操作することで、計算の意味を体感できます。例えば、「ブロックが 個と 個あったら合わせていくつ?」と尋ね、実際にブロックを並べて数えさせます。
- お菓子や果物: 分数の導入に最適です。「ケーキを 等分したら、一つ分はどれくらい?」と実際に分けてみたり、「お菓子が 個あって、 人で同じ数ずつ分けるには?」と割り算の概念を教えることもできます。
- お金: 金銭感覚を養うだけでなく、足し算や引き算、繰り上がり・繰り下がりの計算練習にもなります。「 円と 円を合わせるといくら?」「 円のものを買って、 円出したらいくらお釣りがくる?」など、具体的な場面設定で練習させます。
- 図形:
- 積み木やブロック: 立体図形を組み立てたり、分解したりすることで、見えない部分を想像する力を養います。展開図を実際に作ってみるのも良いでしょう。
- 折り紙: 図形の対称性や、角度、面積の概念を視覚的に理解するのに役立ちます。
- 身近な形: 家の中にあるもので、「これはどんな形?」「四角形はどこにあるかな?」と探す遊びを通じて、図形への興味を高めます。
- 量と測定:
- 水や砂: 「コップ 杯分の水はペットボトルにどれくらい入るかな?」と実際に量を測ってみることで、かさの概念を理解します。
- メジャーや定規: 物の長さを測ったり、身長を測ったりすることで、長さの概念を身につけます。
- 時計: 短針と長針がそれぞれ何を表しているのか、午前と午後の違いなど、具体的な生活の中で時間を意識させることが大切です。一緒に料理をする際にタイマーをセットする、お風呂の時間を計るなど、日常的に使ってみましょう。
図や絵を描く習慣づけ
文章題が苦手な子の多くは、問題文を読んでも頭の中でイメージができない傾向があります。そこで、問題文を読んだら必ず図や絵を描く習慣をつけさせましょう。
- 例題: 「リンゴが 個あります。そこから 個食べました。残りのリンゴは何個ですか?」
- リンゴを 個描く 食べた 個にバツをつける 残りを数える。
- 例題: 「一本 円の鉛筆を 本買いました。全部でいくらになりますか?」
- 円の鉛筆を 本描く それぞれに 円と書き込む 足し算や掛け算で合計を出す。
図や絵にすることで、問題の状況を視覚的に把握でき、必要な情報と不必要な情報を見分けたり、どのような計算をすれば良いのかを具体的に考える手がかりになります。この習慣は、高学年で学習する複雑な問題(割合、速さ、グラフなど)にも応用できる、非常に重要なスキルです。
2. 楽しく、無理なく継続できる学習環境作り
短時間集中型学習
お子さんの集中力は長く続きません。特に算数が苦手な場合は、**「短時間集中型」**で学習を進めるのが効果的です。
- 1回あたりの学習時間: 分から 分程度に設定し、その時間内は算数に集中します。
- 休憩: 短い学習時間の後には、必ず休憩を挟みましょう。休憩時間には、好きなことをさせて気分をリフレッシュさせます。
- 区切り: 学習内容を細かく区切り、「今日はこの問題だけ」「このページのここまで」というように、小さな目標を設定することで、達成感を味わいやすくします。
長時間の学習は、お子さんの集中力を切らし、算数への嫌悪感を増幅させる原因にもなります。**「もっとやりたい!」**と、少し物足りないくらいで切り上げるのが理想的です。
成功体験を積み重ねる
「できた!」という成功体験は、お子さんの自信と学習意欲を高める最高の薬です。
- スモールステップ: 難易度の高い問題ばかりに挑戦させるのではなく、**「少し頑張ればできる」**レベルの問題から始めましょう。簡単な問題でも、正解できたら大いに褒めてあげます。
- 褒め方: 結果だけでなく、**「よく考えたね」「最後まで諦めずに取り組んだね」**など、努力の過程を褒めることが大切です。具体的な行動を褒めることで、お子さんは「また頑張ろう」という気持ちになります。
- 間違いは学びのチャンス: 間違えた時こそ、成長のチャンスです。「どうして間違えたんだろう?」「次はどうすれば良いかな?」と、一緒に原因を探り、次につなげる姿勢を大切にしましょう。決して叱らず、「これは良い練習問題だね!」と前向きな声かけを心がけます。
ゲーム感覚で算数に触れる
学習を遊びの中に組み込むことで、お子さんは抵抗なく算数に親しむことができます。
- 市販の知育玩具や算数ゲーム: 計算パズル、立体パズル、図形ブロックなど、遊びながら算数の力を養えるおもちゃを活用しましょう。
- ボードゲームやカードゲーム: オセロや将棋、トランプなどは、論理的思考力や集中力、数を扱う力を養います。特にトランプの「神経衰弱」や「ババ抜き」は、数の認識や短期記憶に役立ちます。
- お買い物ごっこ: 金銭計算の練習になります。おもちゃにお店の値札をつけ、親子でお客さんと店員になってやり取りをすることで、足し算、引き算、お釣りの計算を実践的に学ぶことができます。
- 料理のお手伝い: 材料の分量を計ったり、時間を計算したりする中で、量や時間の概念を自然と身につけられます。
- 身の回りの算数: 「今、何時何分?」「あと何分でご飯かな?」「このお菓子、 人で分けるにはどうしたらいい?」など、日常会話の中で算数的な問いかけを意識的に取り入れましょう。
3. 教材選びと効果的な使い方
基礎固めを重視した教材選び
算数が苦手な場合は、まず基礎を徹底的に固めることが重要です。
- 簡単なドリルや問題集: 学校の教科書準拠のドリルや、計算練習に特化したドリルなど、難易度が低く、反復練習ができるものを選びましょう。
- 繰り返し学習できる教材: 同じ問題を何度も繰り返し解くことで、定着度を高めます。計算であれば、毎日決まった量をこなす習慣をつけるのも良いでしょう。
- 学年を遡る勇気: もしお子さんが現在の学年の内容でつまずいているなら、思い切って前の学年の教材に戻ることも検討しましょう。どこでつまづいたのかを見極め、その部分から丁寧に学び直すことが、結果的に近道になります。無理に先に進めようとすると、さらに苦手意識を深めてしまいます。
教材の進め方と見直し
教材を効果的に使うには、進め方と見直し方が重要です。
- 完璧主義にならない: 一度にすべてを理解させようとせず、**「 割理解できればよし」**という気持ちで取り組みましょう。大切なのは、毎日少しずつでも継続することです。
- 間違いノートの活用: 間違えた問題は、そのままにせず、必ず**「間違いノート」**を作り、後で見直せるようにしておきましょう。
- 間違いノートの作り方: 問題をノートに書き写す 自分の間違いを赤ペンなどで修正する なぜ間違えたのか、どうすれば正解できたのかを簡単にメモする。
- 定期的な見直し: 定期的に間違いノートを見返し、同じ問題が解けるか確認することで、弱点を克服できます。
- 時間制限を設ける: 計算問題などでは、ストップウォッチを使って時間を計り、徐々に時間を短縮していく練習も効果的です。集中力が高まり、計算スピードも向上します。ただし、最初は焦らせないよう、ゆとりを持った時間設定にしましょう。
- 答え合わせは自分で: 自分で答え合わせをすることで、どこを間違えたのかを意識しやすくなります。間違いを発見したら、すぐに直すのではなく、もう一度自分で考えさせる時間を設けましょう。
学習塾を上手に活用する方法

ご家庭でのサポートも大切ですが、専門家である学習塾の力を借りることも有効な手段です。
1. 学習塾選びのポイント
お子さんの状況に合わせたコース選び
一口に学習塾といっても、様々な形態があります。お子さんの性格や学習状況に合わせて選びましょう。
- 個別指導塾:
- メリット: 先生が一人のお子さんに対してつきっきりで指導してくれるため、お子さんの理解度に合わせて、遡り学習や先取り学習など、きめ細やかな指導が可能です。質問しやすい環境で、苦手な部分を重点的に克服できます。引っ込み思案なお子さんや、集団授業についていけないお子さんに向いています。
- デメリット: 費用が集団塾に比べて高くなる傾向があります。
- 集団指導塾:
- メリット: 複数のお子さんが一緒に授業を受けるため、切磋琢磨する環境があります。費用も個別指導塾に比べて抑えられることが多いです。他の子からの刺激を受け、学習意欲が高まることもあります。
- デメリット: 一人ひとりの理解度に合わせた指導は難しく、ついていけないと置いていかれてしまう可能性があります。
- タブレット学習塾・オンライン学習塾:
- メリット: 自宅で好きな時間に学習できるため、通塾の負担が少ないです。自分のペースで進められるものが多く、映像授業で繰り返し学べるものもあります。
- デメリット: 自己管理能力が求められます。質問対応やモチベーション維持の点で、対面での指導に劣る場合があります。
算数に特化した指導体制
算数に苦手意識があるお子さんの場合、算数に特化した指導や、苦手克服に力を入れている塾を選ぶと良いでしょう。
- 基礎からの徹底指導: 概念理解を重視し、基礎の基礎から丁寧に教えてくれる塾が理想です。計算練習だけでなく、図形や文章題に強い指導法があるかを確認しましょう。
- 教材の質: 塾独自の教材や、市販の教材をどのように活用しているかを確認します。苦手な子向けに、スモールステップで進められる教材があるかどうかもポイントです。
- 講師の質と相性: 講師がお子さんの学習状況をしっかり把握し、「なぜ間違えたのか」を具体的に指導できるか、また、お子さんと相性が合うかも非常に重要です。体験授業などを活用し、お子さんが安心して質問できる雰囲気の講師かどうかを見極めましょう。
通いやすさと費用
継続するためには、通いやすさと費用も重要な要素です。
- 立地: 学校や自宅からの距離、交通手段などを考慮し、無理なく通える場所を選びましょう。通塾に時間がかかりすぎると、お子さんの負担になります。
- 時間帯: 習い事や家庭での時間とのバランスを考え、無理のない時間帯で通えるか確認しましょう。
- 費用: 授業料だけでなく、入会金、教材費、季節講習費など、総額でいくらになるのかを事前に確認し、家計に無理のない範囲で選択しましょう。
2. 学習塾の効果的な活用法
塾の先生との連携
お子さんの学習状況を正確に把握し、効果的な指導をしてもらうためには、塾の先生との密な連携が不可欠です。
- 定期的な面談: 定期的に面談の機会を設け、お子さんの塾での様子、学習の進捗、理解度などを詳しく聞きましょう。
- 家庭での様子を伝える: 塾の先生に、ご家庭でのお子さんの学習状況(例:家では計算ミスが多い、文章題を嫌がる、特定の単元でつまずいているなど)を具体的に伝えましょう。家庭と塾が連携することで、よりお子さんに合った指導が可能になります。
- 質問や相談を遠慮しない: 何か心配なことや疑問に思うことがあれば、遠慮なく塾の先生に相談しましょう。塾の先生も、お子さんの成績向上を願っています。
塾の宿題と家庭でのサポート
塾の宿題は、授業で学んだ内容を定着させるための重要なツールです。
- 宿題の管理: お子さんが塾の宿題を計画的にこなし、提出期限を守れるようサポートしましょう。
- 丸つけと見直し: 宿題の丸つけは塾で行うことが多いですが、ご家庭でも一緒に見直し、間違えた問題をなぜ間違えたのか、どうすれば正解できるのかを一緒に考える時間を持つと良いでしょう。
- 無理のない範囲でのサポート: 塾の宿題が多すぎる、難しすぎるなど、お子さんの負担が大きいと感じたら、すぐに塾に相談しましょう。無理強いは、かえって学習意欲を低下させてしまいます。
塾を「活用」するという意識
学習塾は、あくまでお子さんの学習をサポートする「ツール」です。塾に任せっきりにするのではなく、**「どのように塾を活用すれば、お子さんが算数を得意にできるか」**という視点を持つことが重要です。
- 塾で得た知識を家庭で活かす: 塾で新しい解き方や考え方を学んできたら、ご家庭でもその方法を使って問題を解かせたり、解説させたりしてみましょう。
- 塾での成果を褒める: 塾で頑張っていること、少しでもできるようになったことを具体的に褒め、お子さんのモチベーションを維持させましょう。
- 塾だけに頼りすぎない: 塾に通っているからといって安心せず、ご家庭でも引き続き、お子さんの学習状況に目を配り、必要なサポートを続けることが大切です。
算数嫌いを克服するための親御さんの心構え
お子さんが算数を克服するには、親御さんの精神的なサポートが不可欠です。
1. 焦らず、気長に見守る姿勢
算数に限らず、学習はすぐに結果が出るものではありません。特に苦手意識が強い場合、克服には時間がかかります。
- 短期的な結果にとらわれない: 目先のテストの点数や、すぐに計算が速くなることばかりを求めず、**「少しずつでも理解が進んでいるか」「算数への抵抗感が減っているか」**といった長期的な視点で成長を見守りましょう。
- 成長を信じる: お子さんの可能性を信じ、諦めずにサポートを続けることが何よりも大切です。親御さんが焦りや不安を見せると、お子さんにも伝わってしまいます。
2. ポジティブな声かけと承認
お子さんの頑張りや成長を認め、前向きな言葉をかけることで、自己肯定感を育み、学習意欲を高めます。
- プロセスを褒める: 結果だけでなく、「問題をじっくり読めたね」「最後まで諦めずに取り組んだね」「色々な解き方を試したね」など、努力の過程や工夫を具体的に褒めましょう。
- 小さな成長を見逃さない: 「前はできなかったのに、今日はできたね!」「少し計算が速くなったね!」など、ささいな進歩でも具体的に指摘して褒めることで、お子さんは自分の成長を実感できます。
- 「できる!」という自信を育む: 苦手な単元でも、「今は難しいけど、練習すればきっとできるようになるよ」「一緒に頑張ろう」といった前向きな言葉で励まし、自信を持たせましょう。
3. 親子で一緒に学ぶ時間を作る
親御さんが算数に対して興味を持ち、一緒に取り組む姿勢を見せることで、お子さんも算数を身近なものとして捉えやすくなります。
- 一緒に問題に取り組む: 難しい問題があれば、親子で一緒に考えてみましょう。親御さんも悩んだり、試行錯誤したりする姿を見せることで、お子さんも「間違えても大丈夫なんだ」「考えるのは楽しい」と感じるかもしれません。
- 生活の中に算数を見つける: 料理の時に分量を計る、買い物で合計金額を計算する、地図を見て目的地までの距離を考えるなど、日常の中に隠れている算数の要素を一緒に見つけてみましょう。
- 親御さんも学ぶ姿勢: もし親御さん自身が算数が苦手でも、「私も一緒に勉強してみるね!」という姿勢を見せることで、お子さんは「自分だけじゃないんだ」と安心し、一緒に頑張ろうという気持ちになるかもしれません。
4. 完璧を求めない
すべてを完璧にこなそうとすると、親御さん自身も疲れてしまいますし、お子さんにも過度なプレッシャーを与えてしまいます。
- 「 点主義」でOK: 全ての単元を完璧に理解させる必要はありません。まずは苦手な部分を克服し、平均点レベルを目指すなど、現実的な目標を設定しましょう。
- 休むことも大切: 毎日みっちり学習するのではなく、週に 日は算数から離れてリラックスする日を作るなど、メリハリをつけることも大切です。
- 自分を責めない: お子さんが思うように伸びなくても、親御さんが自分を責める必要はありません。お子さんの個性や成長のペースはそれぞれ違います。
おわりに
算数が苦手な小学生のお子さんの学習サポートは、時に根気と工夫が必要です。しかし、今回ご紹介した自宅学習のヒントと学習塾の活用方法を実践することで、お子さんはきっと算数への苦手意識を克服し、楽しみながら学べるようになるはずです。
大切なのは、お子さん一人ひとりのペースに合わせ、「できた!」という成功体験を積み重ねさせること。そして、親御さんが焦らず、気長に、そして何よりも愛情を持って見守り、励まし続けることです。
算数は、日常生活の様々な場面で役立つだけでなく、論理的思考力や問題解決能力を育む上でも非常に重要な科目です。お子さんが算数を通して、考えることの楽しさや、諦めずに努力することの大切さを学んでくれることを願っています。
さあ、今日からお子さんと一緒に、算数という新しい冒険の旅に出てみませんか?
————————————————————————————————————–
学習塾Luce(ルーチェ)
〒306-0225 茨城県古河市磯部1615−1
電話番号: 050-1402-3694
https://luce-dream.com/
古河、結城、八千代町から近くの塾をお探しなら、 学習塾Luce(ルーチェ)がおすすめ!
————————————————————————————————————–